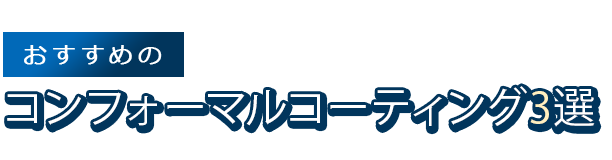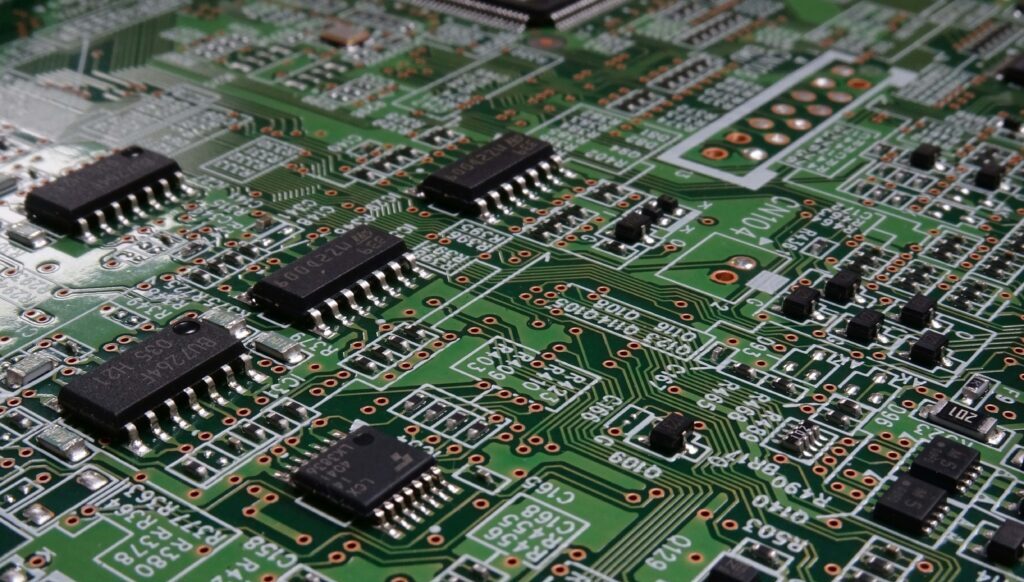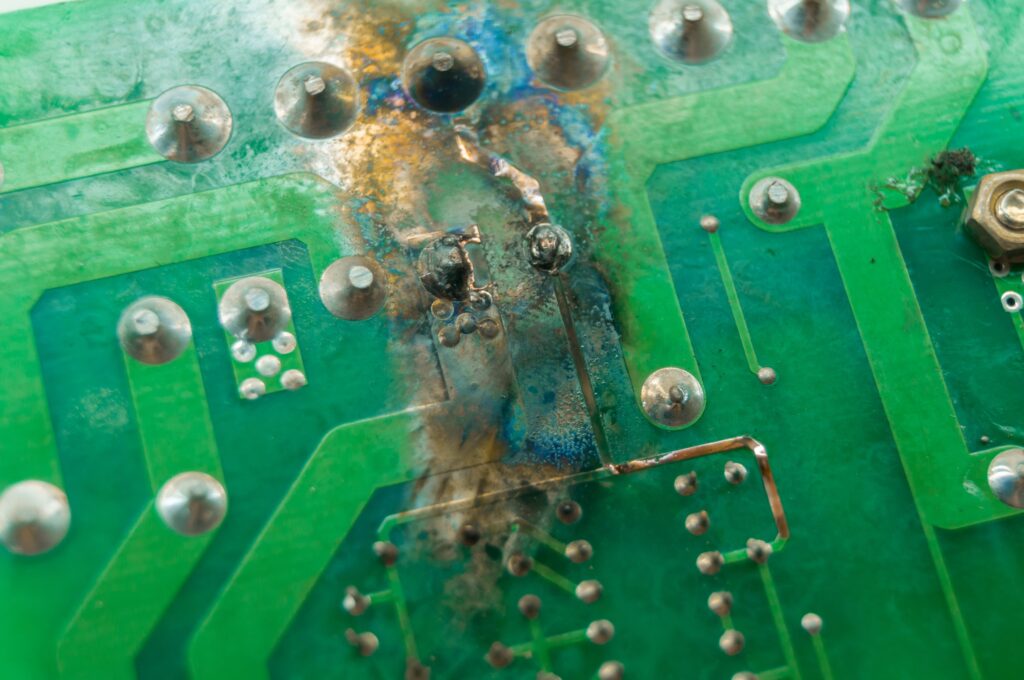環境問題が深刻化する現代において、企業の持続的な事業運営には環境への配慮が不可欠です。こうした背景から、持続可能な社会の実現に向けた「グリーン調達」が注目されています。本記事では、グリーン調達の概要や購入との違い、グリーン調達のメリットについて解説します。この記事を参考に、グリーン調達の理解にお役立てください。
環境にやさしいグリーン調達
地球温暖化や資源エネルギー枯渇などの環境問題が深刻化する中、持続可能な社会の実現に向けた一歩として「グリーン調達」が注目されています。ここでは、グリーン調達の定義や基準、ガイドラインや具体例について解説します。グリーン調達の定義や目的
グリーン調達とは、企業が原材料や部品を調達する際に環境負荷の軽減を目的とし、CO2排出量の少ない素材やリサイクル可能な製品を優先的に選ぶ取り組みです。グリーン調達の取り組みは、企業のグループ全体で環境負荷を低減し、持続可能な生産活動を促進することにより、企業のブランドイメージ向上にも貢献します。
また、企業の作業工程だけに留まらず、原材料や部品にも意識を向けることで、環境意識の高い消費者も安心して購入できる製品づくりが実現します。
さらに、グリーン調達の取り組みは、環境保全だけでなく、企業の社会的責任を果たすうえでもたいへん重要です。グリーン調達は1社だけで完結せず、納入企業や製造企業が団結して製品を見直し、環境配慮の観点から情報共有を行うことが求められます。
グリーン調達の基準とガイドライン
適切にグリーン調達を進めるためには、明確な基準やガイドラインが必要不可欠です。グリーン調達の基準が示されているガイドラインは、環境省が交付する「グリーン調達ガイドライン(暫定版)」に定められています。環境省が提供するガイドラインの基準として、製品製造におけるライフサイクル全体での環境負荷低減や化学物質の管理、再生可能資源の使用などが定められています。
また、ガイドラインでは、製品製造における環境負荷基準で計測するだけでなく、取引先全体の環境経営についても正しく評価し、原材料や部品の調達を考慮することが重要視されている点も特徴です。
これにより、取引先の企業もグリーン調達基準を構築し、環境経営の推進が実現します。企業やその取引先は、ガイドラインにもとづき、調達先の選定や製品評価を実施し、環境に配慮したサプライチェーン全体を構築します。
グリーン調達の具体例
グリーン調達の具体例として、堀富商工の包装資材に使用するラミネートシート「ホリグリーン」が挙げられます。包装資材に使用されるラミネートシート「ホリグリーン」は、石油系ポリエチレンをサトウキビ由来のグリーンポリエチレンに置き換え、CO2排出量を最大70%削減しています。性能は従来品とほぼ同等で、環境負荷の低減に大きく貢献しています。二酸化炭素を多く排出する石油系ポリエチレンを使用したラミネートシートを環境負荷の少ないホリグリーンに置き換えることで、二酸化炭素排出量の削減やカーボンニュートラルの推進を実現します。
グリーン調達を進めるためのステップ
グリーン調達を導入するには、まず自社における原材料や部品の調達方針を見直し、環境に配慮した基準を設けることが必要不可欠です。次に、取引先企業が行っている環境負荷低減や環境配慮への取り組みに関する情報を収集し、その取り組みを公平に評価します。そのうえで、グリーン調達に関する情報共有を行い、取引先企業と連携しながら環境に配慮した製品開発を進めていきます。このようなステップを踏むことで、グリーン調達の実効性を高めることが可能です。
一例として、堀富商工では、環境負荷の低減を目指す企業と連携し、製品製造におけるライフサイクル全体での環境配慮を推進しています。
グリーン調達とグリーン購入はなにが違うの?
グリーン調達とグリーン購入はどちらも環境に配慮した取り組みですが、対象や目的に違いがあります。ここでは、グリーン調達とグリーン購入の違いについて解説します。対象の違い:企業か消費者か
グリーン調達とは、企業(生産者)が原材料や部品を調達する際に、環境負荷を考慮して購入する取り組みのことをいいます。たとえば、製造業者が環境負荷の少ない素材を調達するケースはグリーン調達に該当します。一方で、グリーン購入とは、消費者が商品やサービスを購入する際に、環境に配慮したものを選ぶことです。
たとえば、消費者がエコ認証を受けた製品や省エネ家電を購入することはグリーン購入に該当します。このように、グリーン調達はBtoBと呼ばれる企業間取引、グリーン購入はBtoCと呼ばれる企業と消費者の取引に適用される言葉となります。
目的の違い:環境負荷低減か消費行動か
企業が行うグリーン調達の目的は、サプライチェーン全体における環境負荷の低減です。企業は、製品のライフサイクルや取引先が掲げる環境方針を再評価し、持続可能な生産活動を促進します。一方で、消費者が行うグリーン購入の目的は、自分が持つ環境意識を反映し、環境に優しい製品やサービスの普及を促進することです。
消費者は、エコバッグやリサイクル素材の衣類を購入することにより、環境負荷の低減に貢献します。こういった目的の違いから、グリーン調達は企業戦略、グリーン購入は消費行動に根ざしているといえるでしょう。
実践方法の違い:評価基準と選択肢
企業が行うグリーン調達では、取引先が提供する製品の環境負荷や環境方針を再評価するための基準を設けます。具体的には、環境省が交付するグリーン調達ガイドラインや国際規格である環境ISO14001にもとづき、詳細な調査や監査を行うものです。一方で、消費者が行うグリーン購入では、エコラベルや省エネマークなど、消費者にとって分かりやすい指標をもとに消費行動を行います。消費者はこれらのラベルやマークを参考に、環境に優しい製品やサービスを選ぶことで、環境負荷を低減に貢献します。
企業はグリーン調達を通じて環境負荷低減に対する透明性を高め、消費者はグリーン購入で環境意識の高さを表現するのが特徴です。
影響する範囲の違い:業界全体か個別か
グリーン調達は、環境負荷低減の影響を業界全体に与える取り組みです。企業が環境に配慮した調達を行うことで、取引先や関連企業にも同様の取り組みが波及します。一方で、グリーン購入は個々の消費行動に依存しており、市場の需要を通じて環境に配慮した製品やサービスの普及を後押しする働きです。グリーン調達とグリーン購入は、相互に補完し合い、持続可能な社会の実現に貢献します。
グリーン調達を行うメリット
グリーン調達は環境負荷の低減だけでなく、企業にとってさまざまなメリットをもたらします。ここでは、グリーン調達がもたらす具体的なメリットについて解説します。ブランドイメージの向上
グリーン調達に取り組む企業は、環境意識の高い消費者や取引先から高い評価を受けています。環境に配慮した製品やサービスを提供することは、社会的責任に対する前向きな姿勢のアピールに繋がり、相対的にブランドイメージが向上します。環境意識の高い企業や消費者に支持されている堀富商工のラミネートシート「ホリグリーン」は、CO2排出量削減に貢献する製品として、ブランドイメージの向上につながった一例です。
企業が行うグリーン調達は、企業の信頼性と市場での差別化に直結するため、安易に軽視できない取り組みだといえます。
コスト削減と効率化
グリーン調達の取り組みは、長期的な企業のコスト削減に繋がります。たとえば、リサイクル素材や省エネ素材を使用したり、エネルギー効率の高い電球や低流量な蛇口を導入したりすることは、原材料費や廃棄費用、水道光熱費の削減につながります。また、グリーン調達を活用した効率的なサプライチェーンを構築することで、物流コストやリードタイムの短縮も可能です。このように、企業がグリーン調達を行うことは、環境に配慮しながらコスト削減と物流の効率化をもたらします。
環境関連の法規制に対する対応力強化
環境関連の法規制は年々厳しくなっており、企業はこれらに適応する必要があります。グリーン調達を推進することで、環境負荷の低い原材料や製造工程を採用しやすくなり、法規制への対応力が強化されます。化学物質の使用制限やCO2排出削減目標に対応するため、環境負荷の低い原材料や製造工程を採用する企業が増えているのがその一例です。また、企業が行うグリーン調達は、規制違反によるリスクも軽減するため、企業の持続可能性を高める効果があります。
市場競争力の向上
グリーン調達に取り組む企業は、環境意識の高い市場における競争力を強化できます。消費者の環境意識が高まるなか、エコラベルや省エネマークなどエコ認証を受けた製品やサービスの需要は、増加の一途をたどっています。堀富商工の「ホリグリーン」が、環境に配慮した包装資材として市場で高い評価を受けていることは、グリーン調達の結果として市場競争力が向上した一例です。このような製品は、環境志向が高い消費者や企業との取引拡大につながり、市場での競争優位性を確立します。