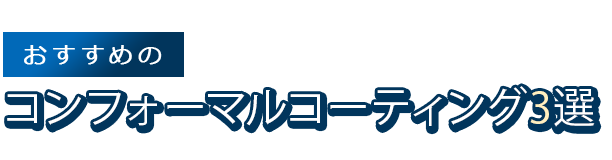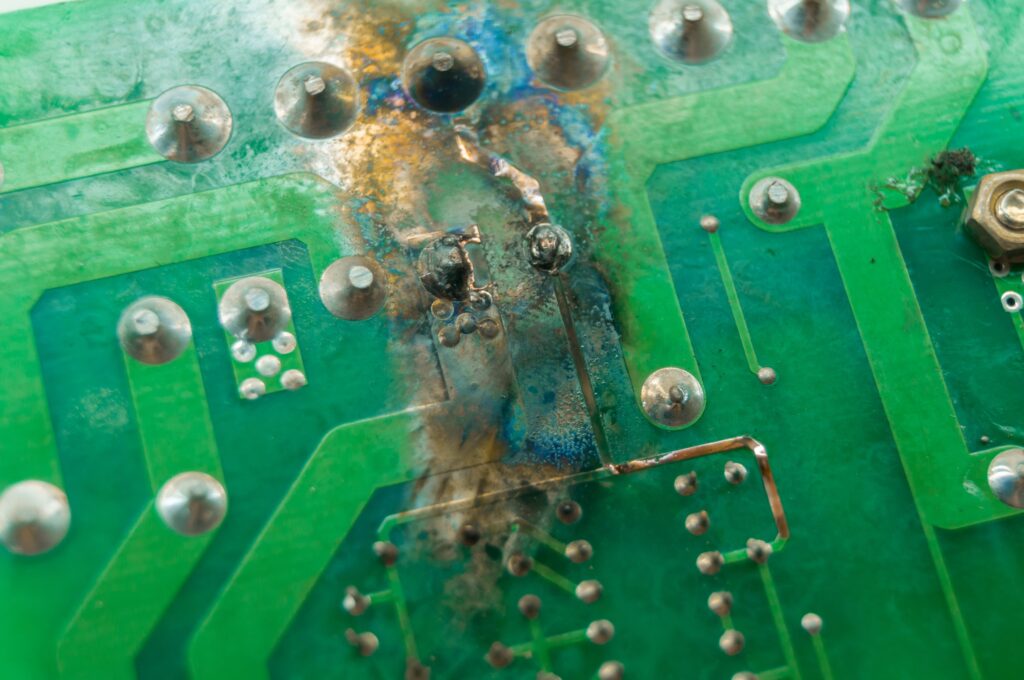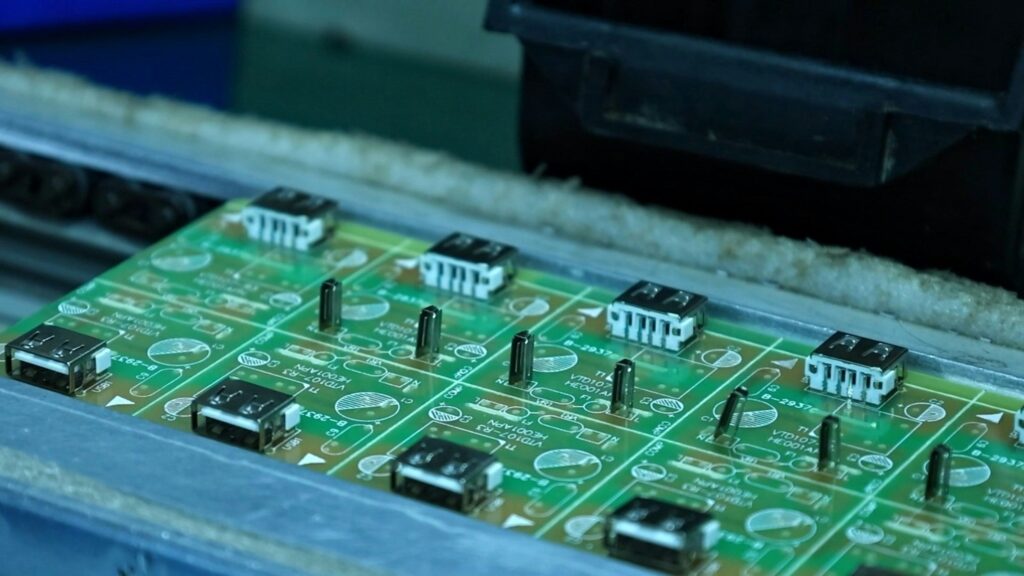PRTR制度は、特定の有害性をもつ化学物質の排出量を集計・公表する、法律で定められた制度です。事業者にとって、化学物質の適切な管理と事業の透明性は、社会的責任を守るうえで欠かせません。この記事では、PRTR制度と対象物質、そして企業が注意すべき点についてわかりやすく解説しているので、ぜひ参考にしてください。
PRTR制度と対象になる化学物質
私たちの身の回りには、多くの化学物質が使われており、これらなしでは社会活動は成り立ちません。これら化学物質は便利で必要不可欠な反面、取り扱いを誤ると環境や健康に悪影響をおよぼすことがあります。そうしたリスクを抑えるため、日本では「PRTR制度(化学物質排出移動届出制度)」が導入されています。有害物質を届け出る仕組み
PRTRは「Pollutant Release and Transfer Register」の略称で、法律上の正式名称は「化学物質排出把握管理促進法(化管法)」、略して「PRTR法」と呼ばれることも多いです。これは、事業で取り扱う有害性のある化学物質について、その排出量や移動量を国に届け出て可視化する仕組みです。この制度の対象となる事業者は、国に対し、物質がどれだけ排出されたか、廃棄物としてどこに移動したのかを報告する義務があります。届出された情報は国が集計し、さらに家庭や自動車など、事業者以外の排出量を推計したうえで一般に公開されます。
公開により、誰でも、どこからどのような化学物質が、どのくらい排出されているかを確認可能となり、化学物質に関する監視の仕組みとして機能しているのです。
環境保護の動きにより誕生した
PRTR制度の考え方は、国際的な環境保護の動きがベースになっています。制度の原型は1970年代のオランダ、そして80年代のアメリカで始まり、92年の「環境と開発に関する国際連合会議」で採択された「アジェンダ21」や「リオ宣言」などにより、世界的に環境保護の必要性が認識されました。現在では、経済協力開発機構加盟国を中心に多くの国で導入され、日本は99年に法制度として取り入れました。日本のPRTR制度は、世界的な環境保護の動きを受けて誕生したのです。
対象となる化学物質
PRTR制度の対象となる化学物質には、どのようなものがあるのでしょうか。現在、日本で指定されている対象物質は、化管法で定められた「第1種指定化学物質」と呼ばれるもので、その数は515物質にのぼります。さらに、その中でも注意が必要とされているのが「特定第1種指定化学物質」です。これは発がん性など、より深刻な健康リスクが確認されている23物質で、より厳格な管理が求められている物質です。代表的な物質には、石綿、六価クロム化合物、カドミウム、鉛化合物、ベンゼン、ホルムアルデヒドなどが含まれます。
また、ダイオキシン類やクロロエチレン(塩化ビニル)、ニッケル化合物なども該当し、工場や研究所などでの取り扱いには注意が求められます。制度の対象となった場合には届出が必要となるため、使用した量はしっかりと記録しておかなければなりません。
PRTR制度の対象になる事業者
PRTR制度は、化学物質による環境負荷を抑制し、持続可能な社会を築くことを目的とした仕組みです。化学物質の排出量や移動量について事業者が把握し、国に届け出る義務があるこの制度では、対象となる事業者の範囲が明確に定められています。ここでは、対象となる事業者について解説します。24業種が対象となる
対象とされるのは、定められた24の業種に該当する事業者です。これには金属鉱業、石油・天然ガス鉱業、化学製品や塗料、プラスチック、金属製品の製造業をはじめ、印刷、機械器具の製造、建築資材関連の業種など、化学物質の取り扱いが日常的に発生する業種が含まれています。また、たとえ主業務でなくても、該当する業種を一部でも兼ねている場合はPRTR制度の対象です。たとえば、対象外の企業が該当化学物質を使用している場合、それが制度の対象になるケースもあります。
従業員が21人以上
従業員数が21人以上の事業者が対象です。人数には、本社だけでなく、全国にある支社や出張所、工場などの全拠点の従業員を合算してカウントします。たとえば、工場に10人、本社に15人の従業員が勤務している場合、合計で25人となるため、PRTR制度の届け出義務が生じます。従業員数は法人単位でカウントされる点に注意が必要です。
取扱量が1トン以上
PRTR制度の対象となるかは、化学物質の年間取扱量にも関係しています。PRTR制度では、「第1種指定化学物質」と呼ばれる有害性をもつ物質を対象にしており、これらの化学物質を年間1トン以上取り扱う場合が制度の対象です。また、さらにリスクの高い「特定第1種指定化学物質」に該当する物質を0.5トン以上取り扱った場合、事業者は対象業者となり、報告義務が課されます。
このようにPRTR制度は、化学物質を「どれだけ使用しているか」という実量に基づいて適用されます。したがって、実際の作業で使用する化学品が液体や混合物である場合には、成分分析や比重の計算が必要不可欠です。誤差のないデータの把握が、制度遵守のために重要です。
PRTR制度で何を届け出ればいいのか
PRTR制度(化学物質排出移動届出制度)は、化学物質の環境への排出状況を明らかにし、リスクを明確化するための仕組みです。そのために事業者は、化学物質をどれだけ使用し、環境中に排出または事業所外に移動させているのかを毎年届け出ることが義務付けられています。では、制度対象の事業者となった場合、具体的に何を届け出る必要があるのでしょうか。
事業者名について
届出には、事業者名や工場名などの事業所名、所在地、従業員数、業種区分など、事業所に関する基本情報も記載する必要があります。これらの情報は、制度の実効性を担保するために欠かせない要素であり、すべての届出は年に1回、都道府県の窓口を通じて経済産業省へ提出されます。排出量と移動量
また内容には、対象となる化学物質の排出量と移動量の両方が含まれます。排出量とは、空気中や水域、土壌など環境中に放出された量のことで、塗装工程で揮発した有機溶剤が空気中に出た場合などが該当します。一方、移動量は、廃液や廃棄物として事業所の外に運び出された分です。使用済みのコーティング剤を含む廃液を産業廃棄物として処理業者に引き渡した場合、その量が移動量としてカウントされます。
排出量や移動量の計算には、経済産業省と環境省が提供している「PRTR排出量等算出システム」を利用するのが効率的です。このツールを使えば、化学物質の種類や使用工程ごとに、比較的正確な推定値を算出でき、事業者の負担を軽減できるので便利です。
営業秘密がある場合
また、届出情報の中に営業秘密に該当する内容が含まれる場合は、通常の手続きとは異なり、事業所を所管する大臣に直接提出することが認められています。所管大臣は、その内容を環境大臣と経済産業大臣に伝えます。営業秘密がある場合は、都道府県の窓口ではなく、事業所所轄大臣へのルートで提出することも可能なので、必要に応じて選択しましょう。
公表
届けられたデータは、物質別、業種別、地域別といった分類で集計され、広く一般に公表されます。都道府県や所管大臣は、これらのデータをもとに、地域のニーズに応じて集計・分析し公表可能です。さらに国は、PRTR制度の届出対象外である家庭や農地、自動車などからの排出量についても独自に推計して公表しています。加えて、集計されたデータを活用し、環境モニタリングや健康影響の調査なども実施しています。国民が個別の事業所の情報を知りたいときは、情報公開請求により開示を求めることも可能です。
自分は関係ない?届出で注意すべきポイント
「PRTR制度(化学物質排出移動届出制度)」と聞くと、大規模な化学工場や専門的な製造業だけに関係があるものと思われがちです。しかし実際には、もっと身近な業種や中小規模の事業者も対象になる可能性があります。PRTR制度の対象であることを知らずに届出を怠った場合、罰則が科される恐れもあるので注意が必要です。ここでは、届出を含めPRTR制度で注意すべきポイントについて解説します。
違反には過料が課される
PRTR法(化管法)に基づく届け出を怠ったり、虚偽の内容を報告したりした場合には、20万円以下の過料が科されることがあります。過去には、実際の排出量より少なく報告していた企業が、8万円の過料処分を受けた事例も報告されています。制度を軽視した対応は、企業イメージの毀損にもつながりかねないため、リスクを軽減する手段として、PRTR制度の対象外となる「非該当品」を活用することも検討しましょう。
PRTR対象化学物質を含まない代替品を導入することで対象事業者から外れ、届出義務そのものを回避できる場合があります。こうした選択により、行政手続きの簡略化だけでなく、地球環境への配慮にもつながります。
アプリでかんたんに検索できる
制度により集められた化学物質に関する情報は、経済産業省と環境省が共同で運用する検索ツール「PRTRけんさくん」によって、一般に公開されます。「PRTRけんさくん」は、誰でもインターネット上でアクセスできるアプリケーションで、事業所の所在地や名称を入力することで、その事業所がどんな化学物質を扱っているのか、どれだけ排出しているのかが一目でわかります。
つまり、届出を実施すれば、その内容は地域の住民を含む不特定多数の人々に共有されることになるのです。有害な価格物質を扱う事業者は、法に従って適切に届け出ることはもちろん、自分たちの事業が一般社会の安心・安全にかかわる行動であり、つねに監視の目があるということを覚えておきましょう。